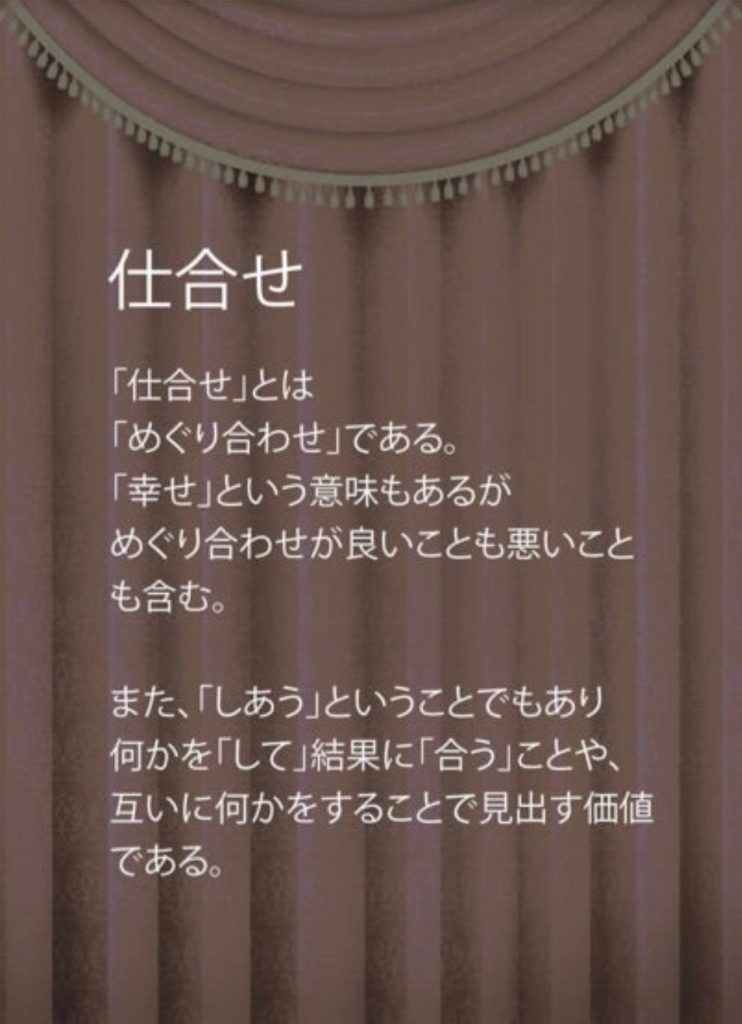本日6月15日、西願寺にて、ごく内々の法要を取り行いました。ひとつは、祖父母(西願寺先々代29世夫婦)の25回忌。もうひとつは、先々々代・西願寺28世住職の80回忌でした。
西願寺28世住職は、私にとって「血のつながり」はありません。しかし、岐阜県から祖父母夫婦を養子に迎え、金森家の姓を継がせ、今の家系を かたち造って下さった方になります。
先祖とは、血だけではなく「縁」で繋がるもの。決して知らない人ではなく、今を生きる私達と深く関係した方々なのです。つまりこの方がいなければ、今の金森家、そして今の私、親族は存在しないのです。そう考えると感謝しかありません。
本来、25回忌や80回忌という法事は一般的ではありません。ですが、あえてこの節目で いとこの方々に声をかけました。
なぜか。
親族もそれぞれに歳を重ね、病気や衰え、不安定な環境におかれている者も増えてきました。そんな中で「ゆっくり顔を合わせる時間を取りなさい」「2年後の法事では遅い、今のタイミングだ!」とインスピレーションが降りたのです。またそれが、初代や祖父母の願いにも感じました。
そしてもうひとつ。
私がこの30年、僧侶として歩んできた中で辿り着いた大きな気付きがあります。それは「法事をやることには、はっきりとした功徳がある」ということです。
「大難は小難に、小難は無難に変わる」
これは、僧侶として30年間歩んできた私の実感であり、最大の悟りでもあります。
法事(読経やお供養)には、時間や費用、気疲れや手間がかかります。けれど、それ以上の尊い意味がある。祖先への感謝を形にし、ご縁のある方々と心を合わせる時間を持つことで「大難は小難に、小難は無難に」変わっていく。そう実感してきました。また、そういうお家を何軒も拝見してきました。
コロナ禍は 人が集まることを謹慎することがマナーとなってましたので、自粛期間の年回は 自分で読経をしてました。住職ですので しっかりと回向が出来ます。誰にも迷惑を掛けません・・・でも何か違う・・・やはり「集って感謝を仕合せ(しあわせ)る」こそが、本来の法事の意義だと確信したのです。
今日、こうして親族と集い、初代や祖父母を偲び、共に手を合わせられること。そのこと自体が、かけがえのない時間でした。また この功徳は参列の各ご家族にも届き、2年後の法事の際に 仕合せ(しあわせ)を共有できるのです。
やっぱり今でした、やってよかった ♪
これからも、ご縁を大切にし、先祖を敬い、今を生きる人との結びつきを深めて参ります。合掌