お彼岸に入りました。多くの方が墓詣りをされてます。祖父母が墓参りの際、「受けた恩は石に刻み、与えた恩は水に流せ」と言って、墓掃除をしていた事を思い出します。仏教では、どんな小さなことにも必ず原因があると教えられます。自分が恵まれていることにも原因があり、その「原因を知る心」を「恩」といい、この幸せは ” 何のお陰か ” を知り(知恩)、感じ(感恩)、報いる(報恩)よう努めることが非常に大事だと説かれています。
植西聰氏のお言葉です。
「流れる水は腐らず」ということわざがあります。「流れる水」とは、「少しずつでも努力し、前進していくこと」を意味しています。とにかく結果が出なくても、思い通りにならなくても、少しずつでもいいから前進していくことが大切です。あせらずに努力を続けていくことです。そうしていれば「気持ちが腐ることはない」のです。気持ちを腐らせることなく、少しずつであっても前へ向かって進んでいけば、どこかで希望が見えてきます。いい結果に辿り着く一歩手前まで来ていることに気づく場合もあります。大切なことは、止まることなく、前へ向かって歩き続ける、ということです。そして、歩き続けていれば、どこかで目的地に到達できます。それを教えてくれるのが、この「水は腐らず」ということわざです。歩みを止めれば、気持ちがどんどん腐っていくばかりです。(『「水」のように生きる』 ダイヤモンド社)
「流れる水」のように、サラサラと執着を流し、受けた恩だけは忘れない人は素敵です。受けた恩は石に刻み、与えた恩は水に流せ・・・恩の教訓は日本だけの真理ではありません。地球の裏側(ブラジル)にも こんな話があります。5年前、漁村に暮らす ある年配の男性が、油まみれになった瀕死の野生ペンギンを見つけ、懸命に介抱しました。その甲斐あって元気になったペンギンは、やがて名残惜しそうに海に帰っていきます。” もう二度と会うことはないだろう ” と誰もが思っていた次の年・・・なんと、そのペンギンが何百キロも泳いで男性に会いに来たというのです。以後も 毎年やってきたペンギンは、男性にだけ懐き、膝に乗って甘えてきます。そんな帰省は、「ペンギンの恩返し」として話題になっています。
これこそが ” 幸せの循環 ” ですね。お彼岸は恩を知り、感じ、報いる週間です。皆様の現状には 必ず原因があります。その ” 原因=恩 ” を知ると様々なことが好転してきます。どんな状況であれ 恩の歩みを止めなければ、必ずご加護があるのです。感謝の心を持って生きる人の方が、幸福感は大きくなります。合掌


.jpg)
.jpg)



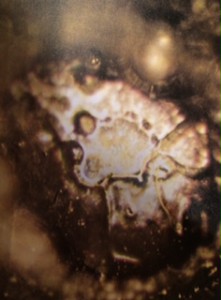


-300x300.jpg)





